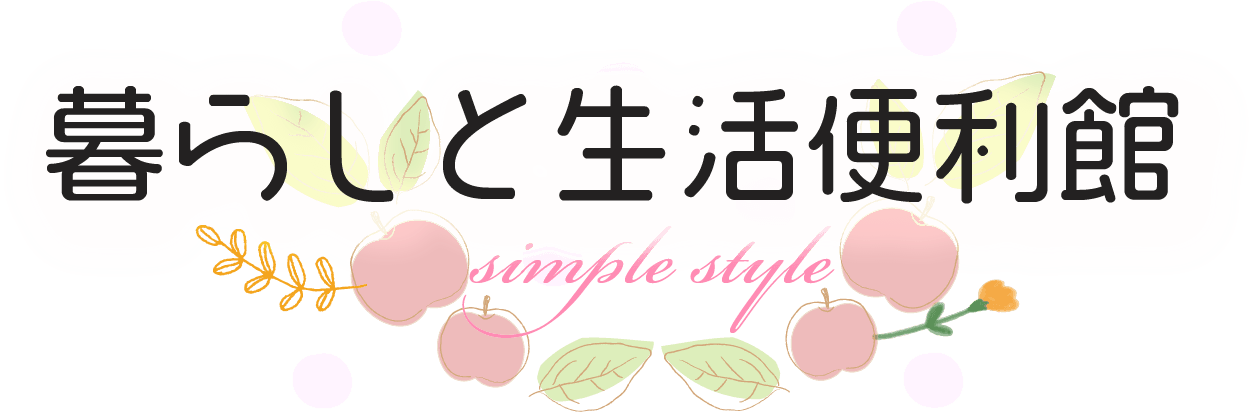介護職の処遇改善は進んでいる?
厚生労働省の調査によると、介護職の処遇改善が徐々に進み、基本給が25万円を超えました。しかし、他産業との賃金格差はまだ大きく、介護報酬制度の仕組みも影響しています。介護職の現状と処遇改善への取り組み、さまざまな職種の仕事内容について解説します。

介護職の現状
介護職の処遇改善
厚生労働省が2024年度の「介護従事者処遇状況等調査」を発表し、処遇改善の新加算を取得している事業所における常勤介護職員の基本給が平均25万3810円に達したことが明らかになりました。前年度から1万1130円(約4.6%)増加したものの、依然として他産業との賃金差は大きいと指摘されています。新加算を取得した事業所は95.5%と高い割合でしたが、訪問リハビリテーションなど一部の種別では取得率が低く、加算取得にばらつきが見られます。
基本給が25万円を超えたが・・・
介護職の基本給が25万円を超えたと聞くと、一見改善が進んでいるように感じますね。でも、この金額で「やっと25万円を超えた」という表現が使われるのは、やっぱり低い水準だなと感じてしまいます。他の産業と比べて、まだまだ厳しい現状です。特に重労働である介護職にとって、この給与水準で働き続けるのは大変なことだと思います。体力的にも精神的にも負担が大きい仕事なのに、それに見合った報酬が支払われていないのは問題ですよね。
しかも、今回の調査結果を見て気になるのは、訪問リハビリテーションなどの一部サービスで新加算の取得率が低いことです。これが何を意味するかというと、同じ介護職でも働き方によって待遇が大きく異なる可能性があるということです。全職員への給与引き上げが58%というのも、決して十分とは言えませんよね。
ただし、改善がまったく進んでいないわけではありません。給与の引き上げ方も「ベースアップ」や「定期昇給」「賞与の引き上げ」など様々な方法で行われています。こうした施策が浸透することで、少しずつ状況は良くなっていくのではないかと思います。
一方で、介護職は今後も需要が増える職業です。高齢化が進む日本では、介護サービスの質を向上させることが非常に重要になります。そのためには、働き手の待遇をしっかり改善していくことが不可欠です。介護職の方々が安心して働ける環境を作ることが、日本全体の課題だと強く感じます。
介護報酬制度
介護職の賃金が他産業より低い理由の一つに「国の介護報酬制度」が関係しています。介護サービスの提供者が受け取れる報酬は国によって定められており、自由に料金を設定できない仕組みになっているためです。これにより、給与改善を行おうとしても利益を大きく上げづらいという問題があります。
また、介護職は労働人口全体に対して高齢者の割合が増加する中で、今後さらに重要視される職業です。介護ロボットやAI技術などの導入も進んでいますが、結局のところ「人によるケア」が必要不可欠な部分が多いです。そのため、待遇改善と働きやすい環境づくりが、これからの日本社会にとって重要なテーマとなるでしょう。
今回のニュースでわかったことは、処遇改善は確かに少しずつ進んでいるけれど、まだまだ十分ではないということです。介護職の方々がもっと安心して働ける環境を作るためにも、国や企業が継続して努力する必要がありますね。
介護職の種類と仕事の内容
- 介護福祉士: 国家資格を持つ介護の専門職。利用者への直接的な身体介護を行うほか、アセスメントや介護計画の立案、チームへの指揮も担当
- 訪問介護員(ホームヘルパー): 利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を提供
- 資格がなくてもできる介護職の補助的業務を担当
- 物品の準備や片付け、食事の配膳・下膳、ゴミ捨て、シーツ交換などが主な業務
- 利用者の身体に直接触れる介助は行わない
- 要介護者・要支援者からの相談を受け、状況に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成
- 市町村・サービス事業者・施設などとの連絡調整も行う
- ケアマネジャーが立てた介護プランをもとに訪問介護サービスの計画を立案
- ヘルパーへの指示や指導を行う
- 利用者や家族へのサービス説明と同意取得も担当
- 施設で働くスタッフや施設全体の管理を担当
- スタッフの労働環境や施設の収益管理、ケアの質の確認などを行う
- 家族からの相談を受け、必要な情報提供や各施設との連携を取る
- 介護老人福祉施設では生活相談員、介護老人保健施設では支援相談員と呼ばれる
- 介護報酬請求事務を中心とした施設の事務作業を担当
- 電話対応、窓口対応、出退勤管理、会計処理、備品管理、書類作成なども行う
- 管理栄養士・栄養士: 利用者の栄養管理や献立作成を行う
- 機能訓練指導員: 利用者の身体能力に合わせた機能訓練計画の作成と実施
- 看護職員: 施設内での利用者の健康管理や服薬管理
- 福祉用具専門相談員: 福祉用具の選定や使用方法のアドバイス
- 介護ドライバー: 通所介護施設などでの利用者の送迎
- 調理スタッフ: 栄養士などが決めた献立に従って調理を行う
よくある質問(FAQ)
介護職の処遇改善加算は、介護職員の賃金改善を目的として国が設けた制度です。記事で触れている「新加算」は、この制度の一環として導入されたもので、取得した事業所では給与の引き上げが行われています。
この加算を取得している事業所では、常勤介護職員の基本給が平均25万3810円になったことが記事でも述べられています。
ただし、訪問リハビリテーションなど一部のサービス種別では取得率が低く、同じ介護職でも働く場所によって待遇に差が生じる可能性があります。
記事で説明されているように、介護職の給与が低い主な理由の一つは「国の介護報酬制度」にあります。介護サービスの報酬は国によって定められており、事業者が自由に料金を設定できない仕組みになっています。
このため、事業者側も給与改善を行おうとしても、利益を大きく上げるのが難しいという構造的な問題があります。
また、処遇改善は少しずつ進んでいるものの、記事にあるように「やっと25万円を超えた」という表現が使われるほど、介護職の給与水準は依然として課題が残っています。
記事の「介護職の種類と仕事の内容」で説明されているように、介護職には様々な種類があり、それぞれ必要な資格が異なります。代表的なものとしては「介護福祉士」という国家資格があり、これは介護の専門職として高く評価されています。
また、訪問介護員(ホームヘルパー)や介護職員初任者研修修了者として働くこともでき、介護補助・介護助手なら資格がなくても始められる場合もあります。
キャリアアップを考えるなら、ケアマネジャー(介護支援専門員)や生活相談員などの資格取得も視野に入れると良いでしょう。記事で紹介されている様々な職種についても参考にしてみてください。